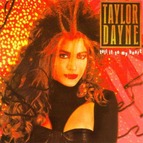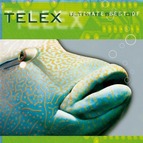鳩が豆鉄砲を食ったようになった――。ある人は息を潜めてそう感想を漏らしたという。1983年10月、妖艶ダンス歌姫、マドンナの台頭によって息を吹き返した米国ディスコ界は、また新たな刺客を迎えようとしていた。ときあたかも、ニューヨーク発ソウル行き大韓航空のボーイング747ジャンボ機が、サハリン沖上空でソ連戦闘機のミサイル攻撃を受けて墜落、乗員29人と乗客240人全員が死亡した事件があったちょうどひと月後のことである。
鳩が豆鉄砲を食ったようになった――。ある人は息を潜めてそう感想を漏らしたという。1983年10月、妖艶ダンス歌姫、マドンナの台頭によって息を吹き返した米国ディスコ界は、また新たな刺客を迎えようとしていた。ときあたかも、ニューヨーク発ソウル行き大韓航空のボーイング747ジャンボ機が、サハリン沖上空でソ連戦闘機のミサイル攻撃を受けて墜落、乗員29人と乗客240人全員が死亡した事件があったちょうどひと月後のことである。米ソ冷戦がなお世界を暗く覆う中、発売されたアルバムは「She's So Unusual」(和訳:彼女はまったくもって変人です。写真)。1953年、ニューヨークに生まれたシンディ・ローパーのデビュー作である。齢三十を超えたばかりの遅咲きポップ歌手だが、ド派手な衣装とメイク、それにちょいと違和感が残るブルージーで高音基調の歌声から繰り出すダンスチューンは、世の若人たちの鬱憤を吹き飛ばすかのごとく、ディスコフロアを席巻したのだから侮れない。
この10曲入りアルバムからは、なんと5曲までもが全米でチャートインした。最初のシングルカット「Girls Just Want To Have Fun」(邦題:ハイスクールはダンステリア、米一般チャート2位、米ディスコチャート1位)は、もう天にも舞い上がるがごとく弾けまくり、踊る者の心を捉えて離さない。私自身、ディスコで初めて聞いた瞬間に、「こんなイカれた曲がまだこの世に存在したのか!」と感動にむせび、不覚にも踊りながら流れる涙が止まらなかった。
その徹底したイカれぶりは当時、圧倒的な勢いでお茶の間に浸透していった音楽番組MTVのPV(プロモーションビデオ)でも確認することができる。まず冒頭、イントロに合わせてシンディが、画面右から「ツツツー」と瞬間移動よろしく滑ってくる場面が印象的だ。そして、主人公の少女役であるシンディの「Have Fun」ぶりは、ラストに向けて加速度的に高まっていく。このビデオには、冒頭から後半まで本物の母親(カトリーヌ・ローパー)が「母親役」で出演していて、我が子の常軌を逸した行動にリアルにあきれる様子も見て取れる。
ほかにも、このアルバムからは「She Bop」(米一般3位、ディスコ10位)というダンスヒットが生まれた。これまた人を食った奇天烈路線を地で行く弾けぶり。とりわけ80年代を代表するディスコリミキサーだったアーサー・ベーカーによる「スペシャル・ダンス・ミックス」は、ディレイやサンプリングなどのエフェクトを駆使しており、踊る者の脳天を揺さぶるような衝撃を与えたものだった。
ただ、彼女は“ディスコ道”にのみ邁進したわけではなかった。実は、意外にもしっぽりバラードなどスロー系が得意なのだ。デビュー作収録の「Time After Time」(米一般1位)と「All Through The Night」(同5位)、それに2作目アルバム「True Colors」の同名曲シングル(86年、同1位)といった珠玉の名曲を数多く送り出しているのである。映画「グーニーズ」の主題歌として知られる「Goony Is Good Enough」(85年、同10位)とか、ブルースロックの雰囲気漂う「Money Changes Everything」(84年、同27位)や「I Drove All Night」(89年、同6位)など、毛色の違う作品もある。
こうした「清濁併せ呑む」姿勢こそが、彼女の真骨頂といってよいだろう。聴いているこちらは、はっちゃけディスコの後にいきなり美メロのバラードが耳に飛び込んでくると、ぽかん顔で目は点になる。けれども、得も言われぬ清涼感が次第に体を包みこむのである。
彼女は幼少時に絵と音楽に目覚め、10代前半にはギターを手に自作の曲を作るなどの活動を始めた。両親が早くに離婚するなど家庭環境は複雑だったが、特に絵は高く評価され、著名な美術系学校に進学したほどだった。ところが、とにかく子供のころから過激な衣装と奇抜なメイクが好きで、周囲からは白眼視されていた。学校は中退してしまい、しばらく愛犬と家出をして、カナダ方面を放浪していた時期もある。強過ぎる個性を持て余し、「アメリカ版尾崎豊」の風情をも帯びながら、自由な表現を求める日々が続いた。
20歳を過ぎたころには、ニューヨークに戻って音楽に没頭。あらゆるアルバイトをして糊口をしのぎながら、地元ロックグループのボーカルなどとして活動した。20代後半になって、個性的な歌声と風貌がようやくメジャーレーベルの目に留まり、鮮烈デビューへと至ったわけだ。晴れてスター歌手の仲間入りを果たし、その絶頂期に参加した85年のあの「We Are The World」でも、サビ直前のブリッジ部分のおいしいパートを担当して好印象を残している。
一時はライバルとも目されたマドンナの音楽には、プロデューサーら制作者側によって「作られた感」が残る。一方、シンディには自作の曲も多く、“一本独鈷”で自ら切り開いてきたいぶし銀の世界観が感じられる。多彩にして繊細。まさに苦労人だからこそ醸すことができる奥行きと味わいを感じさせるのだ。90年代には御多分に漏れず失速してしまったが、80年代を代表する天才異色歌手としての座は、いまも揺らぐ気配がない。